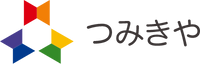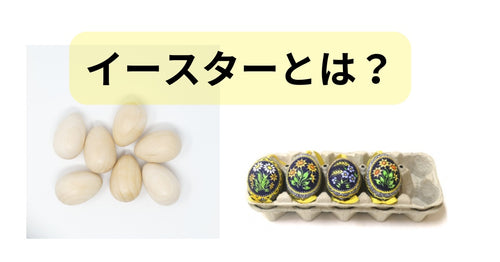当店のオリジナル積み木「てっぺんつみき」が福岡デザインアワードの
最終ノミネート50品に選ばれました。
10月30日に行われる最終審査に向けて準備を進めているところです。
この夏休みも、この積み木を使ったイベントをたくさんご依頼いただきました。
一般的な子どもたちが行う積み木遊びは、子どもたちの自由な発想と
表現が担保されている点に遊びとしての根本的な価値があると思います。
イベントでは、このような自由遊びも展開しつつ、主に小学生以上の場合は
大技や難しい技に「挑戦する」時間も設けています。
子ども時代は特に、自由に遊べる時間を保障することはとても大事なことだと思いますが、
願わくはそれは普段の生活の中で実現できていて、イベントというある意味「ハレの日」には少し普段味わいにくいこともできたらと思っています。
大技や難しい技に挑戦するということは、失敗することと隣り合わせです。
また、自分一人で挑戦することもあれば、みんなで大作に挑戦する時間もあるので、
もしかしたら自分のせいでみんなで作ったものが壊れるかもしれない、という緊張感もあります。
自分の積む作業だけでなく、周りの積む様子にも気を配ったり、
この時間だけでも子どもたちの色々な側面がみれて、
「この子にこんな一面があったんだね」という周りの大人の気づきにもつながったりします。
できれば、子どもたち自身にもちょっとドキドキしながらやってみることの中に、
新たな発見があれば嬉しいものです。
それにしても、子どもたちに挑戦を促すのは容易なことではありませんね。
基本的には強制がかなり難しい分野のことではないかと感じます。
楽しそうな雰囲気の中、やってみたいという気持ちが起きるのを待つしかないでしょうか。
秋の運動会シーズンで、先日地元の地区の運動会がありました。
小学校1年生の長女も参加できる種目があり、大袈裟にいうと挑戦を求められる場面がありました。
といっても、自由参加で、競争的な要素も全くない、僕からすると、プレッシャーとは無縁のような場面です。
それでも、長女は割と頑なに「やらない」といってあまり前に出て行くことはありませんでした。
恥ずかがっているというのとも微妙に違うのです。恥ずかしがっていないわけでもないのですが。
自由参加なのでやらされることでもないのですが、親にするとなんとも言えないもどかしさがあります。
1年生といえど、もう小学生。大人は環境を用意して、あとはやるかどうかは本人次第、
というのが理想なんだろうと思いますが、現実はなかなか難しいものがありますね。
コラム【原田圭悟の「子育て、日々余裕なし」vol.36】 2025年10月