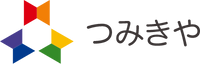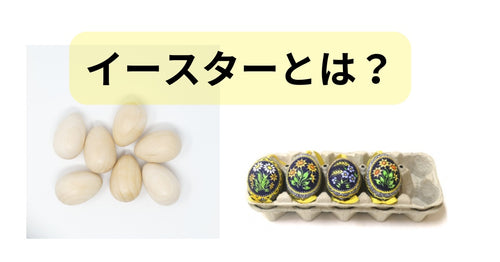こんにちは。スタッフの宮崎です。
本日絵本の会が行なわれました。今回は大人の方が2名。
お2人とも熱心にお話を聞いて意見をかわしあわれていてとても内容の濃い会となりました。



今回は ジャン・ド・ブリュノフ作絵の「ぞうのババール」シリーズです。皆様一度はこのぞうのイラストをご覧になったことがあるのではないでしょうか?ものすごく有名な絵本ですが、絵は見たことあっても読んだことないという方もいらっしゃること思います。私もそのひとりです。
「ぞうのババール」はジャンの息子が病気の時、妻が語って聞かせた象の活躍する物語にヒントを得、息子のアイディアを容れてババールのキャラクターを作ったそうです。シリーズがたくさん出ていますが、ジャンが出した本は5冊のみ。1931年から彼が亡くなる1937年の間に立て続けに5冊発表されています。後は息子さんが受け継いで描かれているとのことです。井上さんによると息子さんが受け継いでいますがジャンが描いた5冊を特に読んでほしいとのことでした。
お話はシリーズとして続いていて、ぞうのババールを主人公に物語は進んでいますが、私たち人間が生きていくなかで経験する日常が細かく表現されていて、かつ押し付けるような表現でなく自然と「そうそう!」と引き込まれてしまうような内容だと感じました。私は「ババールとこどもたち」を聞かせて頂きましたが、3兄妹にはひとりやんちゃものがいるとこやババールとセレストの親としての気持ちや行動が多くのお母さん方が共感するようなお話です。しかしどんなにやんちゃをしても最後はプラスに捉えた愛情表現でしめくくられていて、ジャンの子どもたちへの愛情がとても伝わってくるお話で聞き終わったあとはとても優しい気持ちになりました。
参加者のお一人は「ババール」シリーズをほとんど読まれていて「ババールはもっと小さい大きさの本もでていますが、翻訳されてる方によっても表現が違うと感じました。小さいせいか絵の一部が抜けていたりして子どもが「ここの絵がぬけてるね」と言うんですよ」とおっしゃっていました。確かに翻訳者によって表現が違うことは私も他の本で経験済みでしたのでよく気持ちが分かりました。絵や表現が抜けてしまうことで作者が本来伝えたかったことが伝わらないのは少しさみしいなと感じました。
種類が多すぎて本来お子さんの為に選んで欲しい絵本が選べないことはとてももったいないことです。この会を通してそれぞれの絵本のよいところを知れることで「本物」を子どもたちに届けるきっかけになればと感じました。
次回は10月21日(金)
モーリス・センダックの初期の三部作「かいじゅうたちのいるところ」「まよなかのだいどころ」「まどのそとのそのまたむこう」をご紹介いたします。
今年は最後の会となります。
ぜひお越しください。お待ち致しております。


 今回は ジャン・ド・ブリュノフ作絵の「ぞうのババール」シリーズです。皆様一度はこのぞうのイラストをご覧になったことがあるのではないでしょうか?ものすごく有名な絵本ですが、絵は見たことあっても読んだことないという方もいらっしゃること思います。私もそのひとりです。
「ぞうのババール」はジャンの息子が病気の時、妻が語って聞かせた象の活躍する物語にヒントを得、息子のアイディアを容れてババールのキャラクターを作ったそうです。シリーズがたくさん出ていますが、ジャンが出した本は5冊のみ。1931年から彼が亡くなる1937年の間に立て続けに5冊発表されています。後は息子さんが受け継いで描かれているとのことです。井上さんによると息子さんが受け継いでいますがジャンが描いた5冊を特に読んでほしいとのことでした。
お話はシリーズとして続いていて、ぞうのババールを主人公に物語は進んでいますが、私たち人間が生きていくなかで経験する日常が細かく表現されていて、かつ押し付けるような表現でなく自然と「そうそう!」と引き込まれてしまうような内容だと感じました。私は「ババールとこどもたち」を聞かせて頂きましたが、3兄妹にはひとりやんちゃものがいるとこやババールとセレストの親としての気持ちや行動が多くのお母さん方が共感するようなお話です。しかしどんなにやんちゃをしても最後はプラスに捉えた愛情表現でしめくくられていて、ジャンの子どもたちへの愛情がとても伝わってくるお話で聞き終わったあとはとても優しい気持ちになりました。
参加者のお一人は「ババール」シリーズをほとんど読まれていて「ババールはもっと小さい大きさの本もでていますが、翻訳されてる方によっても表現が違うと感じました。小さいせいか絵の一部が抜けていたりして子どもが「ここの絵がぬけてるね」と言うんですよ」とおっしゃっていました。確かに翻訳者によって表現が違うことは私も他の本で経験済みでしたのでよく気持ちが分かりました。絵や表現が抜けてしまうことで作者が本来伝えたかったことが伝わらないのは少しさみしいなと感じました。
種類が多すぎて本来お子さんの為に選んで欲しい絵本が選べないことはとてももったいないことです。この会を通してそれぞれの絵本のよいところを知れることで「本物」を子どもたちに届けるきっかけになればと感じました。
次回は10月21日(金)
モーリス・センダックの初期の三部作「かいじゅうたちのいるところ」「まよなかのだいどころ」「まどのそとのそのまたむこう」をご紹介いたします。
今年は最後の会となります。
ぜひお越しください。お待ち致しております。
今回は ジャン・ド・ブリュノフ作絵の「ぞうのババール」シリーズです。皆様一度はこのぞうのイラストをご覧になったことがあるのではないでしょうか?ものすごく有名な絵本ですが、絵は見たことあっても読んだことないという方もいらっしゃること思います。私もそのひとりです。
「ぞうのババール」はジャンの息子が病気の時、妻が語って聞かせた象の活躍する物語にヒントを得、息子のアイディアを容れてババールのキャラクターを作ったそうです。シリーズがたくさん出ていますが、ジャンが出した本は5冊のみ。1931年から彼が亡くなる1937年の間に立て続けに5冊発表されています。後は息子さんが受け継いで描かれているとのことです。井上さんによると息子さんが受け継いでいますがジャンが描いた5冊を特に読んでほしいとのことでした。
お話はシリーズとして続いていて、ぞうのババールを主人公に物語は進んでいますが、私たち人間が生きていくなかで経験する日常が細かく表現されていて、かつ押し付けるような表現でなく自然と「そうそう!」と引き込まれてしまうような内容だと感じました。私は「ババールとこどもたち」を聞かせて頂きましたが、3兄妹にはひとりやんちゃものがいるとこやババールとセレストの親としての気持ちや行動が多くのお母さん方が共感するようなお話です。しかしどんなにやんちゃをしても最後はプラスに捉えた愛情表現でしめくくられていて、ジャンの子どもたちへの愛情がとても伝わってくるお話で聞き終わったあとはとても優しい気持ちになりました。
参加者のお一人は「ババール」シリーズをほとんど読まれていて「ババールはもっと小さい大きさの本もでていますが、翻訳されてる方によっても表現が違うと感じました。小さいせいか絵の一部が抜けていたりして子どもが「ここの絵がぬけてるね」と言うんですよ」とおっしゃっていました。確かに翻訳者によって表現が違うことは私も他の本で経験済みでしたのでよく気持ちが分かりました。絵や表現が抜けてしまうことで作者が本来伝えたかったことが伝わらないのは少しさみしいなと感じました。
種類が多すぎて本来お子さんの為に選んで欲しい絵本が選べないことはとてももったいないことです。この会を通してそれぞれの絵本のよいところを知れることで「本物」を子どもたちに届けるきっかけになればと感じました。
次回は10月21日(金)
モーリス・センダックの初期の三部作「かいじゅうたちのいるところ」「まよなかのだいどころ」「まどのそとのそのまたむこう」をご紹介いたします。
今年は最後の会となります。
ぜひお越しください。お待ち致しております。