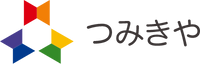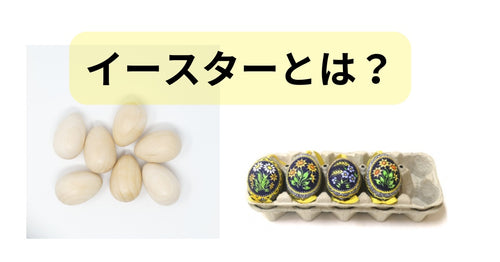小学生になった娘も1学期が無事に今日で終わります。時間が過ぎるのはいつでも早いです。
授業参観に一度出たのですが、算数の時間で45分かけて「長さの比べ方」を勉強していました。2本の紐があって、端っこを揃えて、ピンと伸ばさないと、正しく比較できないよね。端的に言うとたったそれだけのことを45分かけて、授業が進んでいきます。
僕には、ただ何もすることなく45分待っているという時間に感じて、かなりきつかったです。やることないので、かすみの様子を見ていると、やっぱりやることないのか、椅子の前半分を浮かして、ゆらゆら動かし続けていました。
そして他の子を見ると、ほとんど全ての子が少しずつソワソワしています。僕は、全く動かずにいることがとても苦手なのですが、自分は1年生とあんまり変わらないなと思いました。
さて、1年生ってこんなゆっくりなのか、と思う反面、授業は着実に進みます。
ひらがなも知らなかった娘は、1学期でひらがなだけでなく全てのカタカナまで習いました。しっかり着実に進むという偉大さも感じます。
前置きが長くなりました。
今回は父の「思い出のおもちゃたち」というコラムの感想を少し書きたいと思います。
僕の1番の感想は「なんで父は自分の価値観を変えられたんだろう」という疑問でした。
父には多くの短所ももちろんありますが、尊敬しているところがいくつもあります。
そのうちの一つが、大袈裟にいうと「価値観のアップデートを実践しているところ」です。
男尊女卑なんて少し過激な言葉が文章に出てきますが、現在39歳の僕自身も福岡で生まれ育った人間として、年々薄まりつつも、福岡は根強くそんな文化が残っていることを知っています。
僕ですら「男に生まれたからには」「男として」という価値観が自然と身につくのですがから、父の世代はなおさら、です。
自分で言うのもなんですが、僕自身は大人になるにつれ自分自身の男尊女卑的な価値観をかなり変えました。
価値観というのは、自分で気づきにくい特性があるのでまだまだなのかもしれませんが、少なくとも自分自身の常識や価値観を少し客観的に見つめることの大切さを意識しています。
色々な人との出会いで、自分の価値観を客観視しようと思うに至っているわけですが、その最たるロールモデルは父な訳です。
文章に、父は徐々に男尊女卑的な価値観から離れていったとありますが、父の言動行動からは、全く男性優位な匂いを感じません。
おもちゃの話ではないのですが、父に「なぜその価値観を変えられたのか」尋ねてみました。
すると、アトリエニキティキでの仕事の経験が大きかったと思うとの返事。
ニキティキは父がおもちゃに興味を持って転職した玩具の輸入の会社で今もつみきやの最大の取引先でもあります。
当時ニキティキは社長以下ほとんどが女性の会社で、その中で仕事をしていくことが自分の価値観を変えていくことにつながったと思うとのことでした。
当時、兄が生まれて、私が母のお腹の中にいるくらい。父もいい年です。
基本的に福岡にベースがあった父にとって、女性ばかりの職場だけでなく東京という土地も大きな刺激になったのだと思います。
価値観は変えなければいけないものか、と言われるとそうでもないかもしれません。しかし、自分自身がどのような価値観を持っているかを考えない場合、それが原因で周囲や社会と摩擦が起きた時に単に他人のせいにして、辛い人生になりそうです。
全然おもちゃとは関係ない話になりましたが、つみきやとして大事にしたいことでもあります。
また、父のコラムが進めば、息子の立場からの感想もたまに書いてみようと思います。
コラム【原田圭悟の「子育て、日々余裕なし」vol.33】 2025年7月